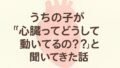豆まきで泣いてしまった息子
「怖いよ…」と抱きついてきた理由
保育園での節分の日、先生から「今日は豆まきをします」と聞いて、朝からソワソワしていた息子。帰宅後、保育園の連絡帳には「鬼が登場すると、泣いてしまいました」との記載が。
迎えに行くと、息子は私の顔を見るなり目をうるませて駆け寄ってきました。
「こわいよ…」と、私の足にぎゅっとしがみついたその姿に、胸がぎゅっとなりました。
聞けば、園の先生が鬼のお面をかぶって部屋に入ってきた瞬間、泣き出してしまったとのこと。
大きな声や見慣れない仮装、そして「鬼=悪いもの」という設定が、まだ小さな心には刺激が強すぎたのかもしれません。
どう声をかけたか
帰り道、私たちはゆっくり歩きながら、今日のことを少しずつ話しました。
「怖かったんだね。びっくりしちゃったんだよね」と、息子の感情をまずは受け止めることに専念しました。
「鬼が来るなんて聞いてなかったし、あんなに大きな声で“おにはーそとー!”って…」
そうつぶやく息子の声には、驚きと混乱がにじんでいました。
私は「怖がらせるために鬼が来たんじゃないんだよ」と、少しずつ話をはじめました。
鬼ってなに?行事の意味を伝える
「心の中のわるい鬼」ってどういうこと?
「節分の鬼ってね、本当は“心の中にいる悪い気持ち”をやっつけるためのものなんだよ」
そう伝えると、息子はキョトンとした顔でこちらを見ました。
「たとえば、すぐに怒っちゃう鬼とか、泣いてばかりの鬼とか、そういう“心の中の鬼”を豆で追い払うんだよ」
この説明が腑に落ちたのか、息子は少しだけ安心したような表情になりました。
「ぼくの中にも、怒りんぼ鬼がいるかも…」とポツリとつぶやいた姿は、親としてなんともいとおしく感じた瞬間でした。
「怖がらせるためじゃないよ」と伝えたかったこと
私は息子に「怖がらせるために鬼がいるんじゃなくて、みんなの心が元気になるように鬼に登場してもらうんだよ」と話しました。
「豆まきは、悪い気持ちを追い出して、いい気持ちで過ごそうねっていう行事なんだよ」と。
すると息子は、「じゃあ、いい気持ちの“にこにこ鬼”になれるようにする!」と、照れ笑いを浮かべながら話してくれました。
節分の意味を少しでも理解して、自分なりに受け止めようとしている姿に、成長を感じました。
その後の様子と息子の変化
「来年は投げてみようかな」と笑った日
その夜、私たちは家でも簡単に豆まきをしてみました。鬼役はぬいぐるみ。
「怒りんぼ鬼、でていけー!」と笑顔で豆を投げる息子の姿に、昼間の涙はすっかり消えていました。
しばらくして迎えた翌年の節分の日。
朝の準備をしていると、息子がぽつりとつぶやきました。
「今年は、ぼくも鬼に豆投げてみようかな」
あの涙の日が、少しずつ乗り越えた経験として、彼の中に積み重なっていることを実感しました。
親として考えた“伝え方”と“向き合い方”
行事を通して心を育てるということ
子どもにとって、節分や七夕、ひな祭りなどの行事は、ただのイベントではなく「心を育てるきっかけ」になることを、今回の経験から改めて感じました。
怖がらせるつもりじゃなかった鬼が、結果として「気持ちを考えること」や「気持ちを言葉にすること」へとつながったのです。
親としての役割は、行事の意味を押しつけることではなく、子どもが自分なりに感じる気持ちを認め、一緒に考えていくことなのだと思います。
来年も、その次の年も。
節分が、ただの「怖いイベント」ではなく、「心の鬼と向き合う日」として、息子の中に優しく根づいてくれたら嬉しいです。
まとめ|行事の意味を親子で一緒に感じてみよう
節分の豆まきで泣いてしまった息子とのやりとりを通して、行事の本当の意味や「心の中の鬼」と向き合う大切さを親子で学ぶことができました。怖がる気持ちに寄り添いながら、無理に正解を押しつけず、一緒に考えていくことで、子どもは少しずつ成長していきます。行事はただのイベントではなく、心を育てるきっかけ。ぜひご家庭でも、意味や願いを語り合ってみてください。