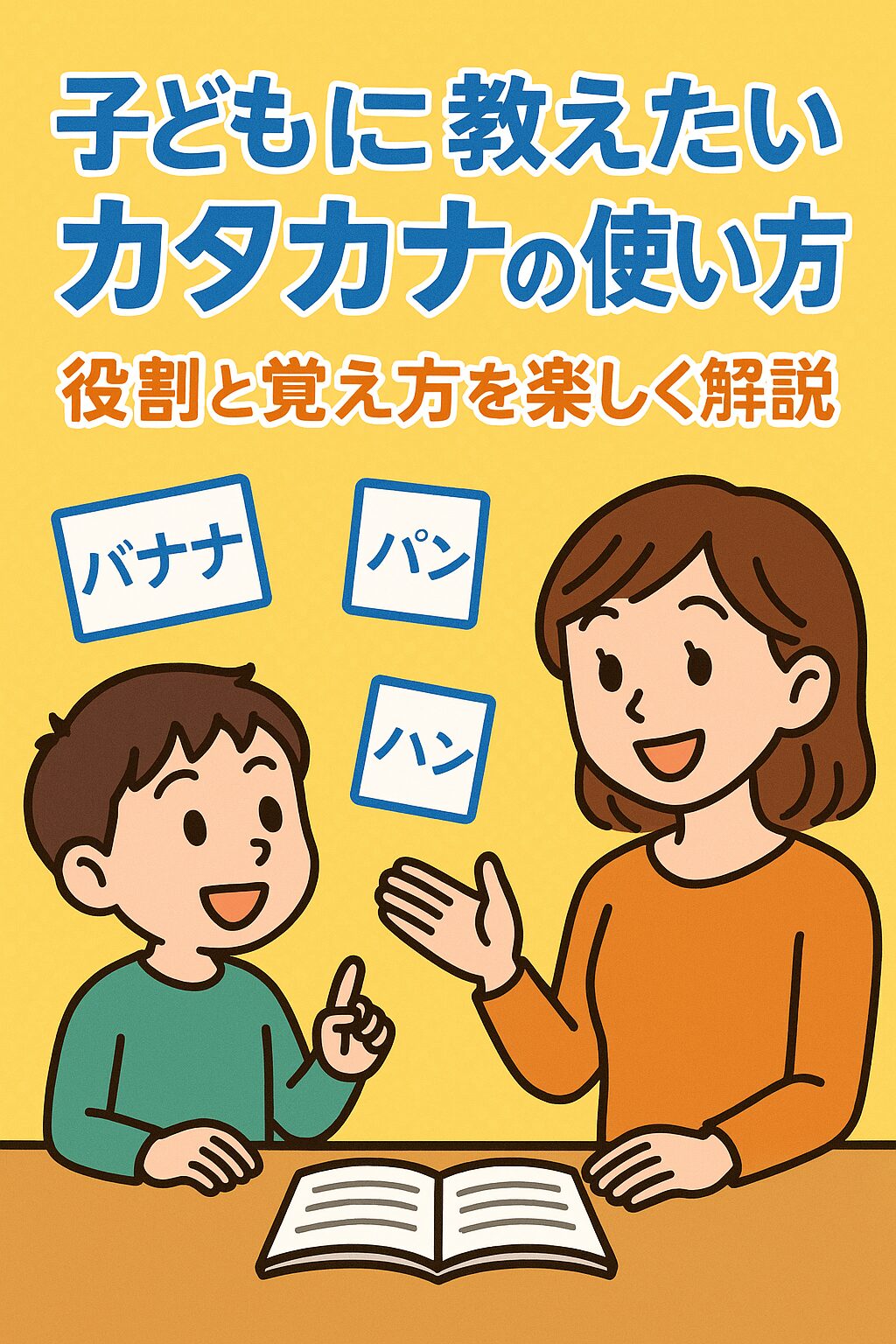「ママ、“コンビニ”ってカタカナでどう書くの?」
ある日、宿題をしていた息子にこう聞かれました。ひらがなは読めても、カタカナって使い方や役割がよくわからないみたい。
確かに私自身も、小学生の頃は「なんでわざわざカタカナで書くの?」と疑問に思っていた記憶があります。
この記事では、カタカナの基本的な使い方から、子どもに教えるときのポイントまで、わが家で実践している声かけ例を交えてお伝えします。
カタカナってどんなときに使うの?

外来語を書くとき
ある日、宿題をしていた息子に「ママ、“コンビニ”ってカタカナでどう書くの?」と聞かれました。
ひらがなはだいぶ覚えたものの、カタカナにはまだ自信がない様子。
私は「カタカナは、外国から来た言葉を書くときに使うんだよ」と教えました。
すると、「どういうこと?」とさらに興味津々。
例えば、
-
コンピュータ
-
バナナ
-
パン
私:「“パン”もカタカナなんだよ」
息子:「えっ?パンって日本語じゃないの?」
私:「昔は“麺麭”って漢字があったけど、パンはポルトガル語から来た言葉なんだよ。だからカタカナで書くんだって」
この話をしたら、「パンってポルトガル語なんだ!すごい!」と目をキラキラさせていました。
こうして教えると、ただ“覚える文字”ではなく、“外国から来た特別な言葉”として認識できるようになるみたいです。
普段の生活の中でも、コンビニやスーパーに行ったときに「これもカタカナだね」と一緒に探すと、自然に覚えていってくれます。
動物や植物の名前を書くとき
我が家では、スーパーに行くと魚売り場で「この魚、カタカナでなんて書くのかな?」とクイズを出すことがあります。
息子も楽しそうにパッケージを見て、
「サバは…サ・バ!」
「マグロは…マ・グ・ロ!」
と、一文字ずつ確認して読んでいます。
たとえば、
-
サバ
-
マグロ
-
カツオ
「なんで魚の名前もカタカナなんだろう?」と息子に聞かれたとき、私はこう答えました。
「外来語じゃなくても、動物とか植物の名前をカタカナで書くことが多いんだよ。
名前を目立たせたり、ひらがなよりスッキリ見えるようにしたりするためなんだって」
すると、「カタカナっておしゃれだね!」と、なんだか誇らしげでした。
絵本や図鑑でも、動物や植物の名前がカタカナで書かれていることが多いので、読み聞かせのときに「これはなんて読む?」と声をかけるようにしています。
擬音語・擬態語を書くとき
「ワンワン」「ガタガタ」など、音や様子を表すときにもカタカナが使われます。
絵本を読んでいると、「ワンワン」「ガタガタ」「ドキドキ」など、カタカナの擬音語がたくさん出てきますよね。
私は読み聞かせをするとき、カタカナで書かれている部分を指でなぞりながら、
「ここは“ドキドキ”って読むんだよ」
「“ワンワン”ってカタカナで書いてあるね」
と教えるようにしています。
息子も、「カタカナで書くと、なんかかっこいいね!」と嬉しそう。
子どもにとっては、“音の言葉=カタカナ”と結びつけると覚えやすいみたいです。
カタカナの役割を子どもにどう伝える?

ひらがなとの違いを説明する
最初は「カタカナ=かっこいい文字」という認識しかなかった息子。
ある日、宿題中に「ママ、この文字ってなんでカタカナなの?」と聞かれました。
私は、どうやって説明しようか一瞬考えたあと、
「ひらがなは日本に昔からある言葉を書くときに使うよね。カタカナは、もともと中国の漢字から生まれて、外国の言葉を書いたり、特別なものを目立たせたりするときに使うんだよ」
と話しました。
すると、息子は目を輝かせて、
「カタカナって外国語用の秘密の文字みたいだね!」
と一言。
「そうだね、秘密の文字みたいでかっこいいよね」と返すと、さらに興味津々に。
子どもって、“特別感”や“秘密のもの”という言葉に弱いですよね。
ただ「覚えなさい」と言うよりも、ちょっとワクワクする表現をしてあげると、一気にモチベーションが上がる気がします。
身近なカタカナを探してみる
我が家では、買い物に行ったときや看板を見たときに「このカタカナ、なんて読む?」とクイズ形式で声をかけています。
例えば、
-
コンビニの看板
-
スーパーの商品パッケージ
-
アニメやゲームのタイトル
この前も、コンビニに入るときに看板を見て、
「この“コンビニ”ってカタカナで書いてあるけど、読めるかな?」と聞いてみました。
息子は少し考えてから、
「コ…ン…ビ…ニ!」
とゆっくり読み上げて、「やったー!」とガッツポーズ。
スーパーでは、お菓子コーナーに行くと「カタカナ探し」が始まります。
「これは“チョコ”だよ」「“ポテト”って書いてある!」と、自分からどんどん読みたがるので、勉強というより遊び感覚で覚えられているようです。
さらに、アニメのタイトルも効果的。
息子は「ドラえもん」や「ポケモン」など、自分の好きなキャラクターの名前だと覚えるスピードが格段に早くて驚きます。
最近では、
「カタカナって楽しいね!もっと読みたい!」
と言ってくれるようになり、親としても嬉しい限りです。
カタカナ学習を楽しくする我が家の工夫
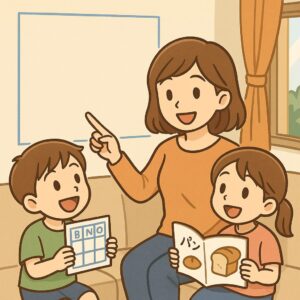
カタカナ表を貼る
わが家では、リビングの机の前にカタカナ表を貼っています。
最初は「邪魔かな?」と思いましたが、宿題中にわからなくなったとき、息子がすぐに見られるので本当に便利。
この前も、「ママ、“ヌ”ってどう書くんだっけ?」と聞かれたとき、
「カタカナ表見てごらん」と声をかけると、
「…あった!こう書くんだね!」と、自分で確認していました。
自分で調べる習慣がつくと、だんだん「わからないから聞く」から「わからないから見てみる」に変わってきます。
この小さな成長が嬉しくて、表を貼ってよかったなと感じています。
カタカナビンゴをする
ひらがなビンゴも楽しいですが、カタカナビンゴになると難易度がぐんとアップします。
わが家では、休みの日にカタカナビンゴをするのが定番。
最初にカードを配るときから、
「ママ、“ホ”ってどれ?」
「“メ”と“ヌ”が似てるけど…あっこっちだ!」
と、文字をしっかり見ながら確認しています。
ゲーム感覚で盛り上がるので、書き方や読み方の復習になるのはもちろん、覚えた文字を使ういい練習にもなります。
負けず嫌いな息子は、「次こそビンゴする!」とやる気満々です。
絵本の読み聞かせでカタカナ探し
普段読んでいる絵本でも、「このページにカタカナ何個あるかな?」とクイズを出すと、息子は真剣な顔で探し始めます。
この前も、「このページに“ン”がいくつあるかな?」と聞いてみたところ、
「えっと…1、2、3…5個あった!」と得意げ。
さらに、「これは“パン”って読むんだよね!」と、自分で読めたことが嬉しかったようで、大きな声で何度も読んでいました。
子どもがつまずきやすいポイントと声かけ例

似た形のカタカナ
カタカナ学習で必ずといっていいほど出てくるのが、「似た文字問題」。
息子も最初、「シ」「ツ」や「ソ」「ン」で何度も間違えていました。
ある日、宿題を見ていたときのこと。
「ママ、“シ”と“ツ”ってどっちがどっちだっけ?」と困った顔。
私:「“シ”は横線が上から降りてきてるイメージ、“ツ”は縦線が横から出てきてるイメージだよ」
そう言いながら、手で空中に書いて見せました。
「シ」は左上から斜めにすっと降りる感じ、「ツ」は右上から横に抜ける感じを強調すると、
息子:「あー!なるほどー!“ツ”は横から出てるね!」
とストンと腑に落ちたようです。
さらに、
私:「“ソ”と“ン”も似てるけど、“ソ”は上から入って左下に抜ける、“ン”は左上から右下に下がるって覚えるといいよ」
息子:「ソは上から!ンは左上から!…うん、わかってきた!」
繰り返し練習しているうちに、書く前に「これは…“シ”…いや、“ツ”か!」と自分で考えるようになってきました。
このように、線の向きや書き始める位置をイメージで伝えると、子どもにはわかりやすいと感じます。
書き順がわからない
カタカナは書き順を間違えても読めることが多いので、つい気にせず書いてしまいがちですよね。
息子も、「読めたらいいでしょ?」と最初は適当に書いていました。
でもあるとき、学校の先生に「書き順が違うと、バランスが崩れてきれいに書けないよ」と言われたそうで、それ以来少し気にするように。
私も「カタカナは書き順を守るときれいに書けるよ」と伝えています。
例えば「ヌ」の場合、最初に左上の点を打ち、次に縦線、最後に横曲線を入れる書き順で書くと、全体が整って見えます。
一緒に練習するときも、
「最後の線はこのくらいの角度にするとかっこいいよ」
「点の位置はここにするとバランスいいね」
と声をかけると、息子も「おお、かっこいい!」と嬉しそう。
カタカナの練習はいつから始める?

年長から少しずつ
息子は年長の終わり頃から、少しずつカタカナに触れるようになりました。
最初はひらがなを覚えるだけでも大変そうだったので、カタカナまで一気にやらせるのはかわいそうかな…と思っていたのですが、絵本やお菓子のパッケージに出てくるカタカナに興味を持ち始めたので、無理なくスタート。
ある日、スーパーのお菓子売り場で
「ママ、“チョコ”ってカタカナでどう書くの?」
と聞かれたことがありました。
「チョ・コって書くんだよ」と教えると、パッケージを指さして「これがチョコかぁ!」と嬉しそう。
読めるようになると、自然と「書いてみたい!」という気持ちが湧いてくるようで、少しずつ書き練習にも取り組むようになりました。
小学校1年生で本格的に
小学1年生になると、学校で本格的にカタカナを習います。
入学前に、簡単なカタカナを少しでも知っておくと授業もスムーズ。
息子も、入学前に「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」くらいは読めるようにしていたので、授業中に「これ知ってる!」と自信がついたようでした。
学校から帰ってくると、
「今日は“カ”と“キ”を習ったよ!」
と嬉しそうにノートを見せてくれたり、
「“ク”と“ケ”がちょっと難しかった…」
と悔しそうに話してくれたり。
こういう小さな積み重ねが、文字を学ぶ楽しさにつながっていくのかなと思います。
もちろん、全部完璧に覚える必要はなく、日々の生活の中で看板やパッケージを一緒に読みながら、「カタカナって便利だね」「かっこいいね」と声をかけることで、自然と覚えていってくれる気がします。
まとめ|カタカナを楽しく学んで自信につなげよう
カタカナは外来語だけでなく、動物や植物、擬音語などさまざまな場面で使います。
ひらがなと違って、なじみが薄い分、子どもにとっては少しハードルが高いかもしれません。
でも、身近なカタカナを探したり、ゲームで楽しく覚えたりすると、自然と身についていきます。
私自身、息子に教える中で「そういえばカタカナってなんで必要なんだろう?」と改めて考えさせられました。
子どもと一緒にカタカナの世界を楽しみながら、日々の学びに活かしていけたらいいですね。