ある日、娘から「なんで電球って光るの?」と聞かれて、私はしばらく考え込んでしまいました。
スマホも家電も当たり前のように電気で動いているけれど、その仕組みをちゃんと説明したことってあまりないかも…。
そこで今回は、子どもにもわかるように「電気とは何か」「どうやって電球が光るのか」を、私の体験や親子の会話を交えながら紹介します。
家庭でのちょっとした実験アイデアも一緒にお伝えするので、親子で楽しく学べます。
電気ってそもそも何?
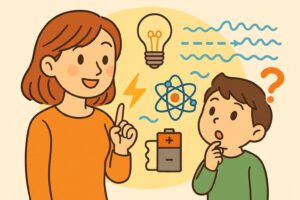
子どもに「電気って何?」と聞かれると、意外と説明に困りますよね。
私も最初は「見えないパワー」と答えたのですが、それでは納得してくれませんでした。
子どもは「どうして見えないの?」「どこから来てるの?」と、さらに質問を重ねてきます。
実は電気は、「電子」というとても小さな粒が動くことで生まれるエネルギーです。
この電子は、私たちの体や空気、机やペンなど、あらゆる物質の中にある原子の一部。
普段は目に見えませんが、電子が一方向に流れると、そこに“電流”が生まれます。
イメージしやすいように、水の流れに例えてみましょう。
川を流れる水を電子に置き換えると、川の流れ=電子の流れ(電流)、水の勢い=電圧、そして川の道筋=電線という具合です。
水が流れれば水車が回るように、電子が流れれば電球が光ったり、家電が動いたりするのです。
そして、この電子の流れを生み出す方法はいくつもあります。
発電所でタービンを回す方法、太陽の光をパネルで電気に変える方法、乾電池の中で化学反応を起こす方法…。
こうして作られた電気は、電線や回路を通って、家庭や学校まで届いています。
つまり電気は、見えないけれど確かにそこに流れていて、私たちの生活を支えるエネルギーの“血液”のような存在なんですよね。
これを知ると、コンセントから電気が来ることが当たり前ではなく、たくさんの仕組みと技術があってこそだと実感できます。
電球が光る仕組み
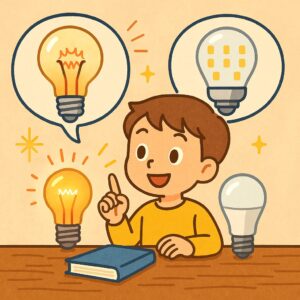
白熱電球の場合
昔ながらの白熱電球は、透明または半透明のガラス球の中に、細くてコイル状に巻かれた「フィラメント」という金属の線が入っています。
このフィラメントの素材にはタングステンという金属が使われており、非常に高い温度にも耐えられるのが特徴です。
電気がフィラメントに流れると、その電気のエネルギーが熱に変わり、温度が一気に2,000度以上まで上昇します。
この高温状態になると、金属は赤や黄色を通り越して白っぽく光り始めます。これが白熱電球の光の正体です。
まるでストーブの電熱線が赤く光るのと同じ現象ですが、白熱電球の場合はさらに高温で、光の量も多くなります。
ガラス球の中は真空か、あるいはアルゴンなどの不活性ガスで満たされています。
これは、フィラメントが酸素と反応して燃え尽きるのを防ぐため。もしガラス球が割れて空気に触れると、フィラメントは一瞬で切れてしまいます。
私が子どもの頃、切れた電球を分解してフィラメントを見たことがあります。
そのあまりの細さと、少しでも触ると簡単に切れてしまう繊細さに驚きました。
白熱電球は、単純な構造ながらも「熱で光を生む」という非常に原始的かつ美しい仕組みなんですよね。
LED電球の場合
一方、今の家庭で主流となっているLED電球は、仕組みがまったく異なります。
LEDとは「発光ダイオード(Light Emitting Diode)」の略で、金属線やフィラメントではなく、特殊な「半導体」が使われています。
半導体には、電気が流れると光を放つ性質を持つ素材があります。
LED電球では、この半導体を通る電子がエネルギーを放出する際に光が生まれる仕組みを利用しています。
この方法は、熱をたくさん発生させずに光を効率よく作れるのが大きな特徴です。
さらに、LEDは色を変えることも得意です。半導体の素材や構造を変えることで、白色だけでなく、赤・青・緑などさまざまな色の光を作ることができます。
照明やイルミネーション、信号機まで幅広く使われているのはこのためです。
発熱が少ない分、エネルギーのロスも少なく、消費電力は白熱電球の約1/6程度。
同じ明るさを出すのに必要な電気の量が少ないので、家庭の電気代削減にも直結します。
「熱よりも光を優先的に生み出す」これがLED電球の最大の強みです。
家庭でできる簡単な電気実験

静電気で電気の存在を感じる
冬場にセーターを脱ぐと「パチッ」とくるあの現象、実は静電気による放電です。
摩擦によって電子が片方にたまり、その差が一気に移動するときに火花や音が出ます。
普段の生活の中でも起きている身近な電気現象ですが、子どもにとっては「見えないけど確かにある」ことを体感できる貴重なきっかけになります。
おすすめは、風船を髪の毛や服にこすりつける実験です。
こすったあとの風船を壁や天井に近づけると、静電気が働いてペタッとくっつきます。
「どうしてくっつくの?」と聞かれたら、「摩擦で電気がたまって、風船と壁が引き合っているからだよ」と伝えてみましょう。
風船の軽さや静電気の力を利用したこの実験は、見た目も楽しく、何度でも試したくなります。
さらに応用として、こすった風船を小さく切った紙片の上にかざすと、紙が風船に向かってピョンと飛びつきます。
これも静電気の引き合う力によるもので、「電気は人や物を動かす力がある」という感覚を実感できます。
電池と豆電球で回路を作る
もう一つのおすすめは、電池と豆電球を使ったシンプルな回路作り。
用意するのは、ホームセンターや100円ショップで手に入る豆電球、乾電池(単三または単二)、そして配線用のコードやワニ口クリップです。
準備ができたら、電池のプラス極とマイナス極をそれぞれコードで豆電球につなぎます。
接続した瞬間、豆電球がパッと光り、子どもの目が輝くはずです。
この実験の良いところは、電気が「回る」という概念を視覚的に理解できること。
電池の向きを逆にするとどうなるか、間にスイッチを入れるとどうなるか、コードを外すとどうなるか…。
そうした変化を一つずつ試すことで、回路の基本や電気の流れ方が自然に身につきます。
安全面では、電池は必ず乾電池を使い、決して家庭用コンセントにはつながないことを徹底してください。
実際に手を動かして「電気はつながって初めて流れる」という事実を体験することが、理解を深める近道です。
子どもに説明するときのポイント

身近な例えを使う
子どもにとって「電気」という言葉は知っていても、その実態は目に見えないため、理解しづらいものです。
そこで効果的なのが、日常の中にある身近なものに置き換えて説明する方法です。
たとえば私はよく「電気は水の流れみたいなものだよ」と話します。
この例えを使うと、電流=水の流れ、電圧=水の勢い(水圧)、電線=水が通るホース、といった具合にイメージしやすくなります。
さらに、家の蛇口を使って説明すると理解度がアップします。
蛇口をひねると水が出る→スイッチを入れると電気が流れる、蛇口を少しだけ開けると水が弱く出る→電圧が低いと光が弱くなる、といった具合です。
「電気は見えないけれど、動きや力の働き方は水と似ている」という感覚を持たせることが大切です。
難しい言葉はあとから
電気の話をするとき、つい専門用語を先に出してしまいがちです。
でも、最初から「電子」「抵抗」「回路」などの言葉を使うと、子どもは意味が分からず混乱してしまいます。
私が心がけているのは、「現象を先に見せる」こと。
たとえば豆電球の実験をして、スイッチを入れたら光る、コードを外したら光らないという事実をまず見せます。
その後で「この電気の流れのことを“電流”っていうんだよ」と名前をつけてあげると、子どもの中で“言葉と現象”が結びつきやすくなります。
また、説明の順番も意識します。
最初は「電気が通る道」「電気が流れる力」など、意味が直感的に分かる言葉を選び、興味や理解が進んできたら「電子」「電圧」「抵抗」といった正式な用語を加えていきます。
この“あとから足す”方法は、子どもの好奇心を途切れさせないコツでもあります。
電気と安全ルールも一緒に教えよう

子どもが電気に興味を持ったときこそ、安全のルールを覚える絶好のチャンスです。
「楽しい」と「安全」を同時に学べば、その知識は長く身につきます。
実験や観察の前に、必ず守るべきポイントを一緒に確認しましょう。
コンセントやコードを濡れた手で触らない
水は電気を通しやすいため、濡れた手でコンセントや電気コードを触ると感電の危険があります。
お風呂上がりや手洗いの後は、必ず手をしっかり拭いてから触るようにしましょう。
特にキッチンや洗面所など水回りでは、コードやコンセントを遠ざける工夫も大切です。
「濡れた手=電気の近くは危ない」という意識を早くから持たせることが安全への第一歩です。
壊れた電気製品は使わない
コードの被覆が破れて中の銅線が見えていたり、異音や異臭がする家電はとても危険です。
放っておくと感電や発火の恐れがあります。
「いつもと違う音や匂いがしたら使わないで教えてね」と声をかけ、すぐに大人が確認する習慣をつけましょう。
子どもには「壊れているものは直してから使う」という基本も覚えてもらいます。
電池は正しい向きで入れる
乾電池には必ずプラス(+)とマイナス(−)の向きがあります。
これを逆に入れると、機械が動かないだけでなく、発熱や液漏れの原因になることもあります。
電池交換のときは、パッケージや本体の表示を一緒に確認する習慣をつけましょう。
「向きを確認してから入れる」ことは、電気を安全に使ううえで欠かせないルールです。
実験は必ず大人と一緒に
豆電球や静電気のような低電圧の実験でも、予想外のトラブルは起こりえます。
例えばコードのつなぎ方を間違えたり、金属部を長時間触って熱くなったりすることもあります。
「やってみたい!」と思ったら、まず大人に相談し、材料や方法を一緒に確認するようにしましょう。
実験中は大人がそばにいて見守り、危険を感じたらすぐに止められる環境を整えることが大切です。
こうしたルールは、説教のように伝えるよりも、実際の場面で一緒に確認しながら教えるほうが定着します。
遊びや実験の中で自然に繰り返すことで、子どもは「安全に楽しむための約束」を身につけていきます。
まとめ|親子で楽しく「電気の世界」へ
電気は、目には見えないけれど生活に欠かせないエネルギー。
そして電球の光には、それぞれの仕組みがちゃんとあることを知ると、普段の暮らしも少し違って見えます。
ぜひ週末に、豆電球や静電気遊びなどの簡単な実験をしてみてください。
「なんで?」という子どもの疑問は、学びの入り口です。
親子で一緒に答えを探す時間が、きっと大切な思い出になります。


