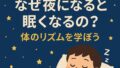「いただきますってなに?」――子どもからの素朴な質問に、うまく答えられますか? この言葉には、食べ物への感謝や命の大切さが込められています。でも、ただ「言いなさい」と教えるだけでは、本当の意味は伝わりません。
この記事では、子どもに「いただきます」の意味をわかりやすく伝える方法や、家庭・保育園での食育の工夫を紹介します。 毎日の食事時間が、心を育てる学びの時間になるように、一緒に見直してみませんか?
「いただきます」の意味とは?
「いただきます」の由来と仏教との関係
「いただきます」という言葉は、日本の仏教文化と深い関わりがあります。元々は「命をいただく」という意味を含んでおり、食材として命を差し出してくれた動植物や、その食材を育て・収穫・調理してくれた人々への感謝を表す言葉とされています。
仏教では「生きとし生けるものすべてに命がある」とされるため、食事とは命をいただく行為。つまり、「いただきます」はその尊さを認識するための大切な言葉なのです。
また、かつては目上の人から物を受け取るときに「いただきます」と頭を下げて感謝する習慣がありました。この文化が食事にも受け継がれ、今のように「食べる前に手を合わせて言う挨拶」として定着したと考えられています。
食事前の挨拶としての「いただきます」
現代では、「いただきます」は単なる食事前の挨拶として定着しています。しかし、その背後には感謝や敬意といった精神的な意味が込められていることを忘れてはなりません。子どもにも「食べ物は当たり前にあるものではない」と伝える第一歩になります。
食卓を囲む前に手を合わせて「いただきます」と言うことで、食事に向き合う心の準備が整います。忙しい日常でも、家族全員で一度立ち止まり、心を整える時間としても重要な意味を持っています。
「いただきます」の言葉の重要性
このひと言があるかないかで、食事の雰囲気は大きく変わります。「いただきます」はマナーでありながら、人としての思いやりを育む機会でもあります。食事に向き合う姿勢を整え、感謝の心を育てる習慣として、非常に重要です。
子どもにとっても、「いただきます」は挨拶の一つという以上に、他者とのつながりを意識する言葉になります。言葉を通じて感謝や礼儀を学ぶことで、思いやりのある行動にもつながっていきます。
「ごちそうさま」との関連性
「いただきます」が始まりの挨拶であるならば、「ごちそうさま」は終わりの挨拶です。どちらも共通して「感謝」を伝える言葉であり、食の一連の流れに対する敬意を示しています。
このふたつの言葉をセットで使うことで、「いただく」→「感謝する」という循環が生まれ、食事を通じたマナーや思いやりが自然と身についていきます。
子どもたちに伝える「いただきます」の意義
家庭での「いただきます」の習慣
家庭こそが、子どもにとって最初の「学びの場」です。食卓での「いただきます」は、親の姿勢がそのまま子どもに伝わります。「ありがとう」と同じように、自然に口にする環境を整えることが大切です。
例えば、「いただきますは、ありがとうの気持ちだよ」と簡単な言葉で伝えることで、子どもは少しずつ意味を理解し始めます。
食卓での会話の中で、「この野菜、誰が作ってくれたんだろうね?」と問いかけるだけでも、感謝の気持ちが育まれます。
保育園での「いただきます」指導案
保育園では、「食べる前に手を合わせて言う」というルールを通じて、集団生活におけるマナーを学びます。先生が言葉の意味を丁寧に伝えることで、形式的なものではなく“心の挨拶”として定着していきます。
また、食事の前に絵本の読み聞かせをしたり、給食を作ってくれた人を紹介する活動なども有効です。子どもたちが「いただきます」の背景を身近に感じられるような工夫がポイントです。
食育としての「いただきます」の取り組み
食育の中で、「いただきます」は大きな柱のひとつです。食材がどこから来たのか、誰がどんな思いで育てたのかを知ることで、食への関心と感謝が深まります。畑で野菜を育てたり、調理に参加する経験も有効です。
また、地産地消の食材を取り入れて「このにんじんは○○さんの畑から来たんだよ」と伝えることで、地域とのつながりや食材の背景に興味を持つきっかけにもなります。
子どもにわかりやすく教える方法
「にんじんさんありがとう」「お魚さんの命をいただきます」といった、キャラクターや絵本を交えた説明が効果的です。難しい言葉ではなく、感情に寄り添った言い方で教えると、子どもは自然に理解し始めます。
具体的には、食材の絵カードを見せながら「これがどうやってここにきたのか、一緒に見てみようね」と対話形式で進めると、食材への関心も高まります。
「いただきます」と食事マナーの関係
食べ物に対する感謝の気持ち
「いただきます」をきちんと言うことで、食べ物への敬意や感謝の気持ちが育まれます。無言で食べ始める習慣では、この大切な心が育ちにくくなってしまいます。
食事の前に少し立ち止まり、「これを作ってくれた人ありがとう」「この食材はどこから来たのかな?」という気持ちを意識することで、日々の食事に感謝の心が生まれます。
「いただきます」が示す料理の大切さ
食卓に並ぶ料理は、さまざまな工程や人の手によって生まれています。それを言葉でしっかりと受け取ることで、「料理を粗末にしない」「好き嫌いを減らす」姿勢につながります。
また、子どもが自分で料理を体験することで、「この野菜を切るのは大変だったけど、おいしくなって嬉しい」といった実感も得られ、「いただきます」の意味がより深まります。
子どもたちとの食事時間の重要性
一緒に「いただきます」と言い、楽しく食事をする時間は、子どもの心を安定させる大切なコミュニケーションの時間でもあります。親子で笑顔を交わしながら食べることで、言葉の意味以上の価値が生まれます。
食事の時間を単なる「栄養補給の時間」ではなく、家族での会話やふれあいの時間にすることで、「いただきます」はより温かい意味を持つようになります。
「いただきます」を通じて学ぶ教養
食材の理解を深めるための絵本
「やさいさん」「おにぎりくんがね…」など、食材の旅を描いた絵本は、子どもの興味を引きながら「いただきます」の背景を伝えるのにぴったりです。視覚的に理解することで、より実感を伴った学びになります。
絵本をきっかけに「この野菜も旅をしてきたんだね」「収穫って大変なんだね」といった会話が生まれると、食材や料理への関心が深まります。
食事を通じた家族の絆
「いただきます」は、家族全員でそろって言うからこそ意味があります。バラバラの時間に食べることが多い現代ですが、少しでも同じ食卓を囲む時間をつくることが、家族の絆を育てるきっかけになります。
毎日でなくても、週に数回は家族そろって「いただきます」を言い、会話を楽しむ時間を持つことで、子どもは安心感を得て、信頼関係もより深まります。
「いただきます」の悪いイメージをなくすには
誤解されやすい「いただきます」の意味
最近では、「宗教的でいやだ」「形式的で意味がない」といった声もあります。しかし、「いただきます」は宗教に限定された言葉ではなく、日本文化の中にある“感謝の挨拶”です。その背景を丁寧に伝えることが、誤解を減らす第一歩です。
特に家庭では、「なぜ言うのか」を子どもと一緒に考える時間を持つと、「言わされている」感覚がなくなり、自発的に挨拶ができるようになります。
挨拶としての「いただきます」を振り返る
私たちは普段、自然に挨拶をしていますが、「いただきます」は特別な挨拶です。目の前にある“命”に向き合い、感謝を忘れない日本人ならではの価値観が詰まった言葉として、もう一度見直す価値があります。
「ありがとう」「ごめんなさい」「おはよう」と同じように、「いただきます」も心を込めて伝えるべき大切な言葉。食事を通して、子どもにその大切さを伝えていきましょう。
まとめ|「いただきます」の意味を一緒に伝えていこう
「いただきます」は、食べ物や作ってくれた人への感謝を表す大切な言葉です。子どもにとっても、日々の食事を通して命のつながりや思いやりの心を育むきっかけになります。家庭や保育の現場で、ただ言わせるのではなく、絵本や体験を通じてその意味を自然に伝えていきましょう。今日の食事からでもすぐに実践できます。まずは、家族で「いただきます」の意味について話し合ってみることから始めてみませんか?