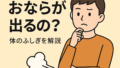春になると「くしゃみが止まらない」「子どもが鼻をぐずぐずさせる」…そんな悩みはありませんか?実は、春は花粉がもっとも多く飛ぶ季節。特にスギやヒノキの花粉は、子どもの体にも大きな影響を与えています。
本記事では、なぜ春に花粉が飛ぶのかという基本から、子どもの花粉症の原因、対策、治療法までをやさしく解説。これを読めば、家族みんなで快適な春を迎える準備が整います。
春に花粉が飛ぶ理由とは?
花粉の基本情報
花粉とは、植物が繁殖のために作り出す非常に小さな粒子で、顕微鏡でしか見えないほど微細です。植物は「受粉」を通して種子を作り、次の世代へ命をつなげますが、そのために花粉を空気中に放出します。
花粉の運ばれ方には主に2種類あり、「虫媒花(ちゅうばいか)」のように虫が運ぶものと、「風媒花(ふうばいか)」のように風に乗って飛ぶものがあります。花粉症の原因となるのは主にこの風媒花による花粉で、空気中を数kmから場合によっては数十km以上も飛散し、人の呼吸や粘膜に入り込んでアレルギー症状を引き起こします。
風媒花の花粉は非常に軽く、量も多いため、目や鼻の粘膜に付着しやすいのが特徴です。しかも一度に数億個という単位で放出されることもあるため、花粉が多い日は空がかすんで見えるほどになります。
植物と花粉の関係
春は植物にとって「目覚めの季節」。冬の間に休眠していた植物が、気温の上昇や日照時間の増加によって活発に活動を始めます。とくにスギやヒノキなどの常緑樹は、この時期に繁殖期を迎え、大量の花粉を空中に放出します。
これには自然の摂理だけでなく、人間の植林活動も関係しています。日本では戦後にスギやヒノキを大量に植林した結果、現在はこれらの樹木が成熟し、一斉に花粉を飛ばすようになったのです。
また、花粉の飛散は天気にも影響されます。特に以下のような条件が揃うと、花粉はより多く、より広範囲に飛びます:
-
晴れて気温が高い日
-
湿度が低く、乾燥している日
-
風が強い日
-
前日が雨で、翌日が晴れた場合(花粉が洗い流された後に一気に放出される)
こうした気象条件が揃う春は、花粉の飛散にとって最も適した時期といえるのです。
春に飛散する花粉の種類
春に飛散する代表的な花粉は以下の通りです:
-
スギ花粉(2月〜4月)
日本の国土の約12%を占めるスギ林から飛散する。特に本州・四国で多く見られ、花粉症患者の約70%がスギ花粉に反応すると言われています。 -
ヒノキ花粉(3月〜5月)
スギに次いで多い原因植物。スギのピークが終わる頃に始まり、5月の連休頃まで続くことがあります。九州や中部地方では飛散量が特に多い傾向です。 -
ハンノキ・シラカンバなどの広葉樹の花粉(主に3月〜5月)
北海道や東北地方では、スギの代わりにこれらの花粉が花粉症の主因となることがあります。シラカンバ花粉は欧米でもアレルゲンとして知られています。
これらの花粉は非常に微細で、1立方メートルあたり数千〜数万個が飛んでいることも珍しくありません。症状が出やすい人は、これらの植物が活動を始める春に、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった典型的なアレルギー症状に悩まされることになります。
子どもの花粉症とその原因
増加する花粉症の傾向
近年、子どもの花粉症が急増しています。ひと昔前までは、大人になってから発症するケースが多かったものの、今では3歳〜5歳の未就学児でも症状が見られることが珍しくありません。
実際、小児科では2月〜4月頃にかけて、目のかゆみや鼻水、咳などを訴える相談が急増し、医師も花粉症の早期発症に警鐘を鳴らしています。
その背景には、以下のような現代特有の生活環境が影響していると考えられています。
-
室内中心の生活:外遊びが減り、自然免疫が育ちにくい
-
過度な清潔志向:除菌・殺菌グッズの多用により、免疫が過剰反応を起こしやすくなる
-
大気汚染やPM2.5の影響:排気ガスや微粒子がアレルゲンと結びつき、症状を悪化させることも
また、生活リズムの乱れやストレスなども免疫バランスを崩す原因となり、花粉症の発症リスクを高めているとされています。
アレルギー反応と体質の関係
花粉症は、花粉を「異物」とみなした体が、それを排除しようとする免疫反応によって引き起こされます。これが、くしゃみ・鼻水・目のかゆみといった症状の正体です。
このようなアレルギー反応は、体質によって大きく異なります。特に以下のような体質や疾患を持つ子どもは、花粉に対しても敏感な傾向があります。
-
アトピー性皮膚炎
-
小児喘息
-
食物アレルギー
これらはいずれも「アレルギーマーチ」と呼ばれるアレルギー疾患の連鎖に関係しており、乳幼児期から注意が必要です。アレルギー体質の子どもは、複数のアレルゲンに反応しやすく、季節性アレルギー(=花粉症)にもなりやすいのです。
加えて、腸内環境の乱れや偏った食生活、ストレスなどもアレルギー反応の誘発要因になるため、体内バランスのケアが重要とされています。
遺伝的要因について
花粉症は体質による影響が大きく、遺伝との関係も深いといわれています。両親のどちらか、あるいは両方がアレルギー体質である場合、子どもも同様に花粉症やその他のアレルギー疾患を持つ可能性が高くなります。
統計的には、
-
片親がアレルギー体質の場合:子どものアレルギー発症率は約30〜40%
-
両親ともアレルギー体質の場合:子どもの発症率は60%以上
といったデータもあります。
もちろん、遺伝だけがすべてではなく、生活環境や食習慣などの後天的な要因も発症に大きく影響します。つまり、「親が花粉症だから仕方ない」とあきらめるのではなく、子どもの生活習慣を整えることで予防・軽減が可能だということです。
花粉飛散の時期と影響
スギとヒノキの飛散時期
春に飛ぶ代表的な花粉として知られるのが「スギ」と「ヒノキ」です。どちらも日本に多く植えられている樹木で、花粉症の原因植物としてもっとも知られています。
-
スギ花粉の飛散時期:2月上旬〜4月中旬
飛散のピークは地域によって異なりますが、関東や関西では3月上旬〜中旬にかけて最も多くなります。スギ花粉は粒子が軽いため広範囲に飛びやすく、都市部にも大量に飛来します。 -
ヒノキ花粉の飛散時期:3月中旬〜5月上旬
スギ花粉のピークが過ぎた頃から本格的に飛散が始まります。見た目や症状に大きな違いはありませんが、ヒノキの花粉に対してのみ反応する人もいるため、スギ花粉が収まっても症状が続く場合はヒノキが原因かもしれません。
この2つの花粉が飛ぶ時期は重なっており、2月から5月までの3ヶ月間にわたってアレルギー症状が出ることも珍しくありません。特に子どもは体調管理が難しい時期でもあり、症状が見られたら早めに対処することが大切です。
地域別の花粉飛散量
日本全国で見ても、花粉の飛散量は地域によって大きく差があります。これは植生の違いや気象条件が関係しており、どの植物の花粉が多く飛ぶかは地域特有の傾向があります。
-
関東・関西・中部地方:スギ花粉とヒノキ花粉が多く、毎年大量飛散が報告されています。特に都市部ではコンクリートやビルの反射によって花粉が舞いやすく、症状が悪化しやすい傾向があります。
-
北海道・東北地方:スギやヒノキは少ない代わりに、シラカンバ(白樺)やハンノキなどの広葉樹花粉が主なアレルゲンとなっています。これらの花粉は4月〜6月にかけて多く飛散します。
-
九州・四国地方:温暖な気候のため、飛散時期が早く、スギ花粉のピークは1月下旬から始まることもあります。長期間にわたって花粉症の対策が必要です。
こうした地域ごとの飛散傾向を把握しておくことで、花粉症の発症時期を予測しやすくなり、早めの対策が可能になります。
花粉の飛散に関する調査結果
花粉飛散の量や時期は、毎年少しずつ異なります。そのため、気象庁や各自治体、医療機関、大学の研究チームなどが毎年飛散量の予測と観測を行っています。
特に注目されているのが、「前年の夏の気象状況」です。
以下のような条件が揃うと、翌年の春の花粉飛散量が増えるとされています。
-
夏の気温が高い
-
日照時間が長い
-
雨が少なく乾燥していた
これらの条件は、スギやヒノキの花芽形成を促進するため、翌春に大量の花粉を飛ばす準備が整ってしまうのです。
さらに、暖冬の年は春の訪れが早まるため、花粉の飛散開始時期も前倒しになることがあります。
また、民間の気象サービスや花粉情報アプリでも、地域ごとの花粉飛散量やピーク時期が随時発表されており、花粉対策を行う上で非常に有用な情報源となっています。
花粉症の症状と見分け方
くしゃみや鼻水の原因
花粉症は、空気中に漂う花粉が鼻や目の粘膜に付着することで起こるアレルギー反応です。体が花粉を「異物=ウイルスや細菌のような危険なもの」と誤認し、それを体外に排除しようと過剰に反応してしまうのです。
主な症状には以下のようなものがあります:
- 連続するくしゃみ
- 透明でサラサラした鼻水が止まらない
- 鼻づまり(特に夜間)
- 目のかゆみや充血
- のどのイガイガ
- 皮膚のかゆみ(顔まわりなど)
- 集中力の低下や不機嫌(特に子どもに多い)
これらの症状は、特に朝起きた直後や外出後に強く出やすいという特徴があります。また、発熱がないのに症状が長く続く場合は、花粉症の可能性が高いと考えられます。
風邪との違い
花粉症と風邪は一見似た症状が多く、特に子どもでは見分けがつきにくいこともあります。しかし、両者には明確な違いがあります。
| 症状 | 花粉症 | 風邪 |
|---|---|---|
| 鼻水 | 水のように透明・サラサラ | 粘り気があり黄色っぽいことも |
| くしゃみ | 連発することが多い | 数回程度、まれに |
| 発熱 | ほとんどない | 微熱〜高熱が出ることも |
| のどの痛み | 軽度またはなし | 強く痛むことが多い |
| 目のかゆみ | よくある | ほとんどない |
| 継続期間 | 数週間〜1ヶ月以上 | 3〜5日で自然治癒することが多い |
また、風邪薬を服用しても改善が見られない場合や、毎年同じ時期に症状が出る場合は、花粉症の可能性が高いと言えるでしょう。
子ども特有の症状
子どもの花粉症は、大人と同じような症状が出ても、自分でうまく言葉で説明できないことが多く、見逃されやすい点に注意が必要です。特に以下のような行動が目立ったら、花粉症のサインかもしれません。
- 目をしきりにこする、まぶたをこすりすぎて赤くなる
- 鼻をすすり続ける、鼻のかみすぎで皮膚がただれる
- 夜に鼻が詰まって寝苦しそうにしている
- 朝起きたときに目や鼻の不快感を訴える
- ぼーっとして集中力が落ちる、イライラしやすい
さらに、子どもの場合は肌が弱いため、顔や耳の周りにかゆみや湿疹が出ることもあります。
保護者が「いつもの風邪と違う」と感じたときは、早めに小児科や耳鼻科を受診することが大切です。
花粉症の体質改善法
花粉症の症状を根本から軽減するには、対症療法だけでなく「体質改善」にも取り組むことが重要です。特に子どもは成長過程にあるため、食事や生活習慣を見直すことで免疫のバランスを整えやすくなります。ここでは、代表的な体質改善法を紹介します。
ヨーグルトの効果
花粉症対策として注目されているのが、乳酸菌を含むヨーグルトの摂取です。腸には免疫細胞の約70%が集中しているといわれており、腸内環境を整えることは、免疫力の向上に直結します。
特に近年では、アレルギー症状を抑制する効果が期待される乳酸菌が研究・商品化されており、次のような種類が人気です:
-
L-92乳酸菌(アレルケアなど)
-
KW乳酸菌(カスピ海ヨーグルトなど)
-
BB536株(ビフィズス菌配合製品)
これらの乳酸菌は継続的に摂取することで効果が期待できるため、1日1個のヨーグルトを毎日習慣にすることが推奨されます。アレルギーを持つ子ども向けのドリンクタイプも市販されており、続けやすさもポイントです。
食べ物での対策
食事からの体質改善も有効です。以下のようなアレルギーに強い体づくりをサポートする栄養素を積極的に取り入れましょう。
-
抗酸化作用のある野菜
ブロッコリー、ほうれん草、にんじんなどにはビタミンC・Eやβカロテンが豊富に含まれており、アレルギーによる炎症を抑える働きがあります。 -
青魚に含まれるEPA・DHA
サバ・イワシ・サンマなどの脂に含まれるオメガ3脂肪酸は、免疫の暴走を抑える効果があり、アレルギー症状の軽減に役立ちます。 -
ビタミンDを含むきのこ類や卵
ビタミンDは免疫機能を調整する働きがあり、アレルギー予防の面でも注目されています。干ししいたけ、まいたけ、卵黄などから摂取できます。
また、食品添加物や過剰な糖分・油分を避けることも、腸内環境の改善に役立ちます。子どものおやつや食事を見直し、なるべく自然な食材を使ったメニューにすることがポイントです。
自然療法の実践方法
薬に頼らず、生活の中でできるナチュラルなケア方法にも効果が期待できます。以下のような自然療法を試してみましょう:
-
甜茶(てんちゃ)やシソ茶を飲む
これらのハーブティーには、ヒスタミンの過剰分泌を抑える働きがあるとされています。砂糖や香料の少ない無添加タイプを選ぶと安心です。 -
規則正しい生活習慣を心がける
十分な睡眠・朝食・適度な運動は、自律神経と免疫バランスを整える基本。特に就寝時間が遅いと、免疫の働きが乱れやすくなるため注意が必要です。 -
深呼吸や軽いストレッチ・散歩
呼吸を整えることで副交感神経が優位になり、炎症反応を抑えやすくなります。気温や花粉量を確認しながら、日中の屋内運動や夜の室内ヨガもおすすめです。
これらは即効性があるわけではありませんが、毎日の積み重ねが体質改善に繋がります。花粉の飛ばない時期から予防的に取り入れておくことで、次のシーズンに向けた備えになります。
花粉症の治療法
花粉症は放っておくと生活の質を大きく下げるだけでなく、学業や仕事、睡眠にも影響します。特に子どもの場合は集中力が低下したり、夜ぐっすり眠れなかったりと、日常生活への負担が大きくなることも。早めの受診と継続的な治療で、症状をコントロールすることが大切です。
クリニックでの受診
花粉症かどうかを見極めるには、耳鼻科や小児科での受診が第一歩です。特に子どもは他の病気との見分けが難しいため、専門的な診断が欠かせません。
医療機関では、次のような検査や対応が可能です:
-
アレルギー検査(血液検査・皮膚テストなど)
スギ・ヒノキ以外にも、ブタクサ・ダニ・ハウスダストなどのアレルゲンを幅広く調べることができます。 -
症状に合わせた処方薬の選定
市販薬よりも症状に合った薬を適切に選べるため、症状のコントロールがしやすくなるというメリットがあります。 -
吸入薬や点鼻薬の処方
鼻づまりや咳がひどい場合には、局所的に作用する薬で負担を和らげることができます。
受診のタイミングとしては、花粉が飛び始める1〜2週間前に診察を受けておくと、予防的な治療ができ、症状の出方が大きく変わります。
医師のアドバイス
花粉症の治療では、症状が出てからの対処だけでなく、「初期療法(予防的な服薬)」がとても重要です。花粉が飛び始める前から薬を飲み始めることで、粘膜の炎症を抑え、症状を軽く済ませることができます。
子どもの場合は以下の点に配慮して、医師に相談することをおすすめします:
-
眠くなりにくい抗ヒスタミン薬を選んでもらう(学校生活に支障が出ないように)
-
粉薬が苦手な場合はシロップタイプで処方してもらう
-
副作用の少ない薬を優先的に使用する
-
目の症状が強い場合は点眼薬の併用も検討する
また、医師は日常生活の注意点や家庭でのケア方法についても具体的なアドバイスをくれるため、定期的な受診が症状管理のカギとなります。
抗体治療の可能性
最近注目されているのが、舌下免疫療法(ぜっかめんえきりょうほう)という「根本治療」に近い方法です。これはスギやダニなど、特定のアレルゲンを少量ずつ舌の下から体内に取り入れることで、アレルギー反応を弱めていく治療法です。
舌下免疫療法の特徴:
-
毎日1回、自宅で簡単に服用できる
-
3〜5年継続することで、体質そのものの改善が期待できる
-
5歳以上の子どもから適応可能(医師の判断による)
ただし、すべての人に適応できるわけではなく、事前のアレルゲン検査や医師の診断が必要です。また、即効性はないため、長期的な計画のもとで取り組む必要があります。
副作用としては、口の中のかゆみや違和感などが出ることもありますが、多くの場合は軽度で済むため、安全性も高いとされています。
花粉症を根本的に改善したいと考える家庭にとって、有力な選択肢のひとつと言えるでしょう。
日常生活での花粉対策
花粉症対策は、薬や治療だけでなく日常生活での工夫が非常に重要です。特に子どもは体が小さく、花粉の影響を受けやすいため、家庭内や外出時の対策が大きな差になります。ここでは、家庭で実践できる具体的な花粉対策を紹介します。
マスクの効果
外出時においてもっとも基本的かつ効果的な対策がマスクの着用です。最近では、花粉やPM2.5に対応した高性能フィルター付きのマスクが多く市販されており、正しく着用すれば吸い込む花粉量を最大で1/6以下に抑えられるというデータもあります。
マスク選びのポイント:
-
不織布マスク:ウイルス・花粉のカット率が高くおすすめ
-
鼻や頬にフィットする立体構造:すき間ができにくく、花粉の侵入を防ぐ
-
子ども専用サイズ:大人用ではすき間ができやすいため、子どもの顔に合ったサイズを選ぶ
最近では、肌が敏感な子ども向けに耳が痛くなりにくいソフトゴムや、抗菌・抗アレルゲン素材を使ったマスクも登場しています。習慣化するために、好きなキャラクター付きのマスクなども活用するとよいでしょう。
外出時の注意点
春先の外出には、花粉が多く飛ぶ日・時間帯を避ける工夫が必要です。
花粉が多くなる条件:
-
晴れて気温が高い日
-
風が強い日(特に午後〜夕方)
-
雨の翌日(空中の花粉が一斉に飛ぶ)
外出時に気をつけたいこと:
-
帰宅したら玄関先で服をはたく:衣類に付着した花粉を家に持ち込まないようにする
-
上着は玄関近くに掛け、室内に持ち込まない
-
目や鼻をこすらない:花粉による炎症を悪化させる原因になるため、我慢させず早めに洗顔やうがいを促す
-
帽子や眼鏡の着用:顔周りに付着する花粉の量を減らすことができる
特に子どもは無意識に目をこすったり、マスクを外してしまうことがあるため、保護者のフォローが大切です。
家の中での対策
外から持ち込まれた花粉は、室内にたまることで長時間にわたって症状を引き起こす要因になります。以下のような家庭内対策で、花粉の滞留を防ぎましょう。
-
空気清浄機の使用
花粉対応フィルター付きの空気清浄機をリビングや寝室に設置することで、空気中の花粉をしっかり除去できます。
※HEPAフィルター搭載のものが効果的 -
布団や洗濯物は室内干しにする
屋外に干すと花粉が大量に付着するため、花粉が多い季節は「部屋干し」が鉄則です。除湿機や扇風機を併用すると、室内干しでも快適に乾かせます。 -
掃除機と拭き掃除の併用
床に落ちた花粉は掃除機で吸い取るだけでなく、水拭きやモップ掃除で静電気による再舞い上がりを防ぐことが大切です。
特に玄関、窓際、カーテンなどの布製品にも注意を払いましょう。 -
加湿器の併用
室内の湿度が40〜60%程度になると、花粉が舞いにくくなり、鼻や喉の乾燥も防げます。
このような「持ち込まない・溜めない・舞い上げない」という3原則を意識することで、家庭内の花粉対策は格段に効果を高めることができます。
花粉症と風邪の見分け方
春先になると、子どもが鼻水を垂らしたりくしゃみを連発する場面が増えます。しかし、それが風邪なのか、花粉症なのか判断に迷う保護者も多いのではないでしょうか。花粉症と風邪は初期症状が似ている一方で、原因も対応法も異なるため、正確に見分けることが大切です。
症状の比較
以下は、花粉症と風邪それぞれの症状を比較した表です。特徴を知っておくことで、見極めがしやすくなります。
| 項目 | 花粉症 | 風邪 |
|---|---|---|
| 鼻水 | 水のようにサラサラで透明。量が多く長く続く | 粘り気があり黄色や緑がかっていることが多い |
| くしゃみ | 1回では終わらず、連続して何度も出る | 単発的に出ることが多い |
| 鼻づまり | よくある。特に夜や朝方に悪化しやすい | あるが、症状の経過とともに改善していく |
| 発熱 | ほとんどなし(あっても微熱程度) | 微熱〜高熱が出ることもある |
| のどの痛み | あまりない。あっても軽度 | 強い痛みを伴うことがある |
| 目の症状 | かゆみ、充血、涙目などが出やすい | ほとんど見られない |
| 継続期間 | 数週間〜1ヶ月以上と長期間続く | 3〜5日程度で自然に治るのが一般的 |
| 時期との関係 | 毎年同じ時期に症状が出やすい | 季節に関係なく感染する可能性がある |
特に「目のかゆみ」があるかどうか、そして「透明な鼻水が長期間続くかどうか」が花粉症の見分けポイントです。また、花粉症は突然発症することも多く、朝起きた直後に症状が強く出る傾向があるのも特徴です。
受診のタイミング
子どもがくしゃみや鼻水を繰り返している場合でも、すぐに花粉症とは断定できません。以下のような条件に該当する場合は、一度小児科や耳鼻科の受診を検討しましょう。
- 1週間以上、症状が続いている
風邪の場合は3〜5日で自然に治ることが多いため、それ以上続く場合はアレルギー性鼻炎や花粉症の可能性が高まります。 - 家族に花粉症の人がいる
遺伝的な要素も大きいため、親や兄弟が花粉症であれば、子どもも発症しやすくなります。 - 毎年同じ時期に同様の症状が出る
「春になると必ず鼻水と目のかゆみが出る」などのパターンがあれば、花粉症の可能性は非常に高いです。 - 市販薬で改善しない
風邪薬を使っても症状が緩和されない場合、原因が風邪ではないことが考えられます。
医療機関では、アレルギー検査によって具体的なアレルゲン(スギ、ヒノキ、ダニ、ハウスダストなど)を特定し、症状に応じた的確な治療や予防策が提示されます。
自己診断の注意点
保護者の中には「とりあえず市販薬で様子を見よう」と考える方も多いかもしれませんが、自己判断で市販薬を長期間使い続けるのは避けるべきです。特に子どもは副作用に敏感なため、合わない薬を使うことで体調を崩す可能性もあります。
また、花粉症の症状がひどくなると、中耳炎や副鼻腔炎といった合併症を引き起こすこともあるため、軽視せずに適切な対応を取ることが大切です。
不安な場合は、早めに小児科や耳鼻科を受診し、専門的な診断とアドバイスを受けることで安心して対処できます。
花粉が飛ぶ理由を知る
花粉症は「春に突然やってくる厄介なもの」というイメージがありますが、実は気象や生態系、人間の暮らしと深く関係しています。なぜ春になると大量の花粉が飛ぶのか、その理由を知ることで、花粉症への理解と対策がより具体的になります。
気象との関係
花粉の飛散量には、その年の天気や気温、湿度、風の強さなどが密接に関係しています。特にスギやヒノキの花粉は、以下のような気象条件で飛びやすくなります:
-
晴れて乾燥している日:湿度が低いと花粉が空気中に舞いやすくなる
-
風が強い日:遠くまで飛ばされるため、広範囲に花粉が届く
-
気温が高い日:花粉が活性化しやすく、飛散量が増える
-
雨の翌日:雨で花粉が一度地面に落ち、翌日晴れると再び舞い上がる「リバウンド現象」が起こりやすい
さらに、注目すべきは前年の夏の天候です。スギやヒノキは、前年の夏に花芽を作ります。以下のような条件が揃うと、翌春の花粉飛散量が増加する傾向があります:
-
夏の気温が高かった
-
日照時間が長かった
-
雨が少なく、乾燥していた
このため、花粉症に悩む人は「夏の暑さ=翌春の警戒信号」と考えておくと、早めの対策が可能です。
生態系の影響
日本の花粉症事情には、戦後の森林政策と生態系の変化が大きく関係しています。戦後の木材需要に対応するため、日本各地でスギやヒノキが大量に植林されました。その多くが今、30〜50年の成熟期を迎え、大量の花粉を生産する状態にあります。
特にスギは「雄花」を大量につけ、1本の木から数千万個以上の花粉を放出するともいわれています。さらに、林業の衰退により間伐(木の間引き)が十分に行われず、密集した人工林が各地に放置されたままになっていることも、花粉の大量飛散を助長する一因となっています。
自然本来の森林バランスが崩れた結果、花粉を出す木ばかりが増えてしまったというのが、日本の花粉症の深刻化の裏にある現実です。
人間活動の影響
意外かもしれませんが、私たちの暮らしそのものも花粉症の原因を悪化させる要因となっています。特に都市部では、以下のような人間活動による影響が指摘されています:
-
大気汚染(排気ガス、PM2.5など)
ディーゼル車などの排気に含まれる微粒子と花粉が結びつくと、アレルゲンの刺激性が高まると言われています。これにより、花粉症の症状が強く出やすくなるのです。 -
住宅密集地での空気の循環不良
ビル風や狭い道路では、花粉が一度入り込むと滞留しやすく、長時間舞い続けることがあります。 -
ヒートアイランド現象による都市の高温化
都市部では地表温度が上昇し、スギ花粉の飛散開始が地方より早まる傾向があります。 -
舗装道路の増加
土や芝生が少ない街では、落ちた花粉が吸収されず、アスファルトの上で舞い上がり続けるため、二次飛散が起こりやすくなります。
こうした人間活動の積み重ねが、花粉症を「現代病」として深刻化させている大きな要因のひとつです。
まとめ|春の花粉対策は「知ること」から始めましょう
春に飛ぶ花粉の正体や、子どもの花粉症の原因を知ることで、適切な対策や治療がしやすくなります。花粉の種類や飛散時期を把握し、日常生活の中でできる予防策を取り入れることで、つらい症状を大きく軽減できます。特に子どもは早めの対応が重要です。
症状が見られたら医療機関に相談し、家庭でも食事や生活習慣を見直して体質改善を意識しましょう。正しい知識で、家族みんなが元気に春を過ごせるようサポートしていきましょう。