子どもが「ママ、日本語と英語ってどう違うの?」と聞いてきたこと、ありませんか?私も娘に聞かれたとき、頭ではわかっているのに、どう説明すれば伝わるのか悩みました。言葉の仕組みって、大人にとっては当たり前でも、子どもには不思議なものなんですよね。
この記事では、日本語と英語のちがいを、家庭での会話や体験を交えながらやさしく解説します。お子さんに聞かれたとき、楽しく答えられるヒントになるはずです。
日本語と英語の「音」の違い

子どもと一緒に英語の歌を聞いていると、「日本語とちがって聞き取りにくい」と感じることがあります。私の娘も「ママ、早口すぎてわからない!」と言っていました。大人でも歌詞カードがないと聞き取れないことがありますから、子どもにとっては余計に難しく感じるのも自然なことです。ここには、言語ごとの「音の仕組み」が大きく関係しています。
母音と子音のちがい
日本語は「あ・い・う・え・お」という5つの母音がはっきりしているのが特徴です。どの音も明確で、口をしっかり動かさなくても聞き取りやすいのが日本語の強みです。たとえば「か」「き」「く」「け」「こ」と発音しても、必ず同じ「あ・い・う・え・お」に母音が収まります。
一方で英語は母音の種類がとても多く、20種類近く存在します。「ア」と「エ」の中間のような音や、「ウ」と「オ」の中間のような音があり、日本語には存在しない微妙な発音がたくさんあります。たとえば「ship(船)」と「sheep(羊)」は、日本人にとっては同じ「イ」に聞こえがちですが、実際には「イ」と「イー」で異なる母音です。こうした違いは、日本語にない音を耳で聞き分ける力が必要になるため、子どもが混乱しやすいポイントでもあります。
さらに英語では、子音だけで終わる音が多く存在します。日本語の「カタカナ英語」では、無意識に「母音」を足してしまうクセがあります。たとえば「cat」を「キャット」と言うように「ト」で母音を加えてしまうのです。この習慣のせいで、英語らしい発音が難しくなることもあります。
単語の切れ方の違い
日本語は「かな」ごとに区切るリズム(モーラ)が基本です。たとえば「アイスクリーム」は「あ・い・す・く・り・い・む」と一音ずつ同じように区切って発音します。どの音も均等なリズムなので、聞き取りやすく、覚えやすい特徴があります。
しかし英語は「強く読むところ」と「弱く読むところ」があるリズム(ストレス)が中心です。すべての音を均等に読むのではなく、ある音を強調し、他の音は短く弱く発音します。たとえば「ice cream」は「アイス」の「アイ」を強く、「クリーム」の「クリ」を弱く発音するリズムになります。この違いを理解していないと、日本語的に「アイ・ス・ク・リ・イ・ム」と平坦に発音してしまい、ネイティブには伝わりにくくなります。
私も娘に「アイスクリーム」を日本語風と英語風で言ってみせたことがあります。日本語的に発音すると「アイスクリーム」。一方、英語的に「アイスクリーム」と強弱をつけて言うと、娘は「え?そんなふうに言うの?」と驚いていました。このとき「英語は歌みたいに強い音と弱い音があるんだよ」と説明したら、とても納得してくれた様子でした。
子どもに伝える工夫
音の違いは説明だけでは伝わりにくいので、実際に聞かせたり、一緒に発音してみるのが効果的です。英語の歌を流しながら「ここが強い音だよ」「この単語は短く言ってるね」と声をかけると、子どももリズムの違いを体感できます。カタカナで書かれた英語に慣れてしまう前に、耳でリズムを感じ取る経験を増やすことが大切です。
文のつくりの違い

日本語と英語は、文の組み立て方が大きく違います。この違いを理解することは、子どもが「どうして英語はこう言うの?」と疑問を持ったときに答えてあげるヒントになります。私自身も娘に説明するとき、まずは日本語と英語のルールを比較してみせることで、すんなり納得してくれる場面がありました。
語順の違い
日本語では「私はリンゴを食べる」と言います。順番は 主語 → 目的語 → 動詞(SOV型)。つまり「誰が」「何を」「どうした」の順に進むイメージです。動作の中心である動詞は最後に出てきます。
一方で英語は「I eat an apple.」のように、主語 → 動詞 → 目的語(SVO型)。つまり「誰が」「どうする」「何を」という順番になります。動詞が真ん中にくるのが特徴です。
このちがいを娘に説明するとき、「日本語は最後まで聞かないと何をするのかわからないけど、英語は途中でわかっちゃうんだよ」と伝えました。すると娘は「じゃあ英語のほうが早く動作がわかるんだね!」と面白そうに反応していました。確かに、日本語は最後まで待たないと動作が決まらないので「サスペンスっぽい言葉」、英語は早い段階で動作がわかるので「テンポのある言葉」とイメージするとわかりやすいかもしれません。
子どもに教えるときは、カードや絵を並べて「I → eat → an apple」と順番に置いてみるのも効果的です。日本語と英語で並べ方が違うことを目で見て確認できるので、理解が深まります。
主語の省略
日本語では「食べたよ」とだけ言っても、誰が食べたのかは文脈でわかります。学校で友達に「お弁当食べた?」と聞かれて「食べたよ」と答えれば、それが自分のことだと理解できます。つまり日本語は、文脈から主語を推測するのが基本になっています。
しかし英語は違います。必ず「I ate」と主語をつけなければなりません。「ate」だけでは「誰が?」が不明確だからです。娘が「なんでわざわざ言うの?」と聞いたとき、「英語では『誰がやったのか』をはっきり言うルールだからだよ」と説明しました。そうしたら「英語はズルできないんだね」と笑っていました。
確かに、日本語は「誰がしたか」を省略しても会話が進みますが、英語では省略すると不自然になります。たとえば「Went to the park.」だけでは正しい文になりませんが、日本語なら「公園行った」と省略しても通じます。ここに大きな文化の違いも隠れています。英語は人や主語を明確にすることで、責任や行動の主体をはっきり示す傾向があるのです。
子どもに伝えるときの工夫
子どもにこの違いを理解してもらうには、実際に日本語と英語の文を比べながら遊ぶのがおすすめです。
-
「私はごはんを食べる」→「I eat rice」
-
「お父さんは本を読む」→「Dad reads a book」
日本語と英語を並べて読み上げると、主語や動詞の位置が違うことに気づきやすくなります。
さらに、主語を省略する日本語と、省略できない英語をあえて比較して「どっちが必要?」と子どもに考えさせるのも効果的です。クイズ形式にすると「英語は必ず主語が必要!」と楽しく覚えてくれます。
私の体験談
私自身、学校で英語を学び始めた頃は、この「語順の違い」と「主語を省略できないルール」でつまずきました。日本語の感覚でそのまま訳すと「I apple eat.」のように不自然になってしまい、先生に直されて恥ずかしい思いをしたこともあります。だからこそ、子どもには「日本語と英語は同じじゃない」と最初から伝えてあげたいと思っています。
娘と一緒に「今日は英語で話してみよう」という遊びをしたときも、最初は「食べたよ」を「Ate!」とだけ言っていましたが、何度か「I ate」と直すうちに、「あ、英語は必ず主語がいるんだね」と自然に気づけたようです。体験の中でルールを感じ取ることが、いちばんの学びになると感じました。
文化や考え方が表れる違い

言語のちがいは、単なる「言葉遊び」では終わりません。その国の文化や考え方、価値観の反映でもあります。私自身、娘と一緒に英語に触れていると、日本語では当たり前だと思っていた表現が英語にはなかったり、その逆もあったりして「なるほど、文化ってこうやって言葉に出るんだな」と感じることがよくあります。
あいさつの違い
日本語で日常的に使う「お疲れさまです」。仕事終わりや学校の後などに自然と口にする表現ですが、英語にはこれにぴったり当てはまる言葉が存在しません。代わりに「Good job!(よくやったね)」や「Take care!(気をつけてね)」のように、状況に合わせて言葉を選んで言い換える必要があります。
つまり、「お疲れさま」という言葉自体が、日本社会に根付いた「一緒に頑張った仲間をねぎらう文化」を反映しているわけです。私が娘に「英語では『お疲れさま』ってどう言うの?」と聞かれたとき、「日本では『がんばったね』をみんなで共有するのが大事だから特別な言葉があるんだよ。でも英語では違う言い方をするんだよ」と説明しました。すると娘は「じゃあ、外国の人は疲れても誰も『お疲れさま』って言ってくれないの?」と少しびっくりしていました。
文化が違うと、励まし方やねぎらい方も変わるのだと気づくことは、子どもにとっても新しい発見になります。
「はい」と「いいえ」の違い
子どもが特につまずきやすいのが、「はい」と「いいえ」の使い方です。
たとえば、日本語で「水を飲まないの?」と聞かれたとき、「はい」と答えると「飲みません」という意味になります。これは、日本語では質問の内容を肯定する形で答えるからです。つまり「飲まないの?」という質問に対して「はい」と言えば、「はい、その通り、飲みません」ということになるわけです。
一方で英語は逆の仕組みです。「Don’t you drink water?」と聞かれたとき、「No」と答えると「飲みません」という意味になります。英語は「自分の意志や事実」を肯定するか否定するかで答えるため、「Yes」は「飲む」、「No」は「飲まない」になります。
この違いを知らないと、「Yes」「No」のやりとりで誤解が生じやすいんです。実際に娘も英語での会話練習のときに、「Don’t you like apples?」と聞かれて「Yes!」と答えたのですが、それは「好きです」という意味ではなく「はい、好きじゃないです」になってしまいます。そのとき一緒にいた先生がやさしく直してくれて、娘は「あれ、逆なんだ!」と大笑いしていました。
こうした経験を通して、「日本語の『はい』は質問に寄り添う答え」「英語の『Yes』は自分の気持ちを表す答え」と意識させると、子どもでも整理しやすくなります。
家庭での工夫
文化や考え方の違いは、説明だけでは理解しにくい部分でもあります。だからこそ、家庭で「場面を想像して遊びながら学ぶ」のが効果的です。
-
「お疲れさま」に代わる英語の言葉を探してみよう
-
「Yes/No」の答え方を日本語と英語で比べてクイズにしてみよう
こうした工夫をすると、単なる暗記ではなく「実際に使える知識」として定着しやすくなります。言葉を通して文化を感じ取ることは、子どもにとって世界を広げる第一歩になるのだと思います。
子どもに伝えるときの工夫

大人にとっては「日本語と英語は違う」というのは当たり前のことでも、子どもにはまだ実感がありません。大人の説明をそのまま伝えても、ピンと来ず「ふーん」で終わってしまうことも多いです。そこで、家庭でできる「楽しく、わかりやすく」伝える工夫が役立ちます。
身近な例でたとえる
抽象的なルールよりも、子どもが目で見て理解できるたとえ話が効果的です。私は「日本語は積み木を縦に積む、英語は横に並べる」と説明しました。すると娘はすぐに「そっか、形がちがうんだ!」と笑顔で納得してくれました。
たとえば、積み木を実際に使って「日本語の文の形」と「英語の文の形」を積み上げてみせるのも楽しい方法です。子どもは具体的なイメージに置き換えると理解がぐんと早くなります。
歌や絵本を活用
耳や目から自然に違いを感じ取れる環境をつくることも大切です。我が家では毎日のように英語の歌をかけ流しています。子どもは歌のリズムに乗って口ずさむうちに、「日本語と違うリズムで言ってるな」と自然に気づきます。
また、英語と日本語が両方書いてある絵本もおすすめです。同じ内容を日本語と英語で読んでみると、語順や言い回しの違いが目に見えて理解できます。特に子どもは絵を見ながら内容を理解するので、「同じ絵なのに言葉の並べ方が違う」ということを体験的に学べるのです。
ゲーム感覚で学ぶ
学びを「遊び」に変えると、子どものやる気は一気に高まります。我が家では「これは英語でなんて言う?」「日本語だとどう言う?」とクイズ形式にして楽しんでいます。正解したらハイタッチをしたり、ポイント制にして競争にしたりするだけで、笑いながら学べる時間になります。
特に、間違えたときに「ちがう!」と指摘するのではなく「おしい!もう一回考えてみよう」と伝えると、子どもも安心して挑戦を続けられます。学びをポジティブな経験に変えることが、継続のカギになります。
家庭での小さな習慣
-
英語のフレーズを1日1つだけ覚える
-
家族で夕食後に「今日の英語クイズ」を出し合う
-
絵本の一文を日本語と英語で読み比べる
こうした小さな習慣を続けると、特別な勉強時間を設けなくても自然に違いを体感できます。大人も一緒に楽しむことで、「親子で成長している」という実感も得られます。
私が実感したこと
娘とこうした工夫を続けていると、「日本語と英語は違う」という理解が、ただの知識ではなく「生活の中で感じること」に変わっていきました。ある日娘が「英語は歌みたいに強いところと弱いところがあるんだよね」と自分から言い出したとき、私は「やっぱり遊びや体験の中で学んだことは残るんだな」と実感しました。
私が感じたメリット
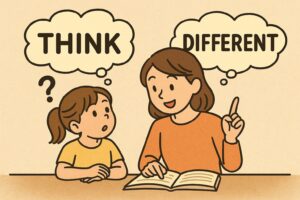
子どもと一緒に「日本語と英語の違い」を学ぶことは、単に語学力を伸ばすだけにとどまりません。むしろ、私が一番大きなメリットだと感じたのは、子どもの「考える力」や「柔軟な視点」が育つことでした。
「なんで?」と考える習慣がつく
娘は「日本語ではこう言うのに、英語では違うんだ」と気づくたびに、「なんで?」と質問してくるようになりました。たとえば、「日本語では主語を言わなくても通じるのに、英語では必ず言うのはなぜ?」と聞かれたとき、私は「英語は『誰がしたのか』を大事にする文化だからだよ」と答えました。
そのやり取りを通して、娘は「言葉ってルールだけじゃなくて、文化や考え方が関係してるんだ!」と理解していきました。「なぜ違うのか」を考える習慣は、語学を超えて、物事を多面的に見る力につながるのだと感じます。
多様な考え方を受け入れる力が育つ
言葉の違いに触れることは、そのまま「自分と違う考え方がある」という学びになります。たとえば、「Yes/No」の違いに戸惑ったときも、「日本語の答え方と英語の答え方はちがうんだね」と気づくことで、「違うやり方があってもいいんだ」と自然に受け入れる姿勢が身についていきました。
娘が「英語はズルできないんだね」と笑って言ったとき、私は「ああ、これはただの言葉の勉強じゃなくて、柔軟な考え方を身につけているんだ」と実感しました。
親子で一緒に学ぶ楽しさ
もうひとつ大きなメリットは、親子で同じ発見を共有できることです。私自身も「お疲れさまです」が英語に訳せないことに改めて気づいたとき、「日本語って面白いね」と娘と笑い合いました。こうした瞬間が、学びを「勉強」ではなく「親子の体験」に変えてくれます。
親が「知らなかった!面白いね」と一緒に驚く姿を見せると、子どもも「学ぶことは楽しいんだ」と感じやすくなります。知識の積み重ねだけでなく、学ぶ楽しさそのものを共有できるのが、家庭で一緒に学ぶ大きなメリットだと思います。
私自身の気づき
子どもと一緒に言語の違いを考えるうちに、私自身も日本語を「当たり前」だと思わなくなりました。今まで無意識で使ってきた言葉に「なぜこう表現するのか?」と立ち止まって考える習慣ができたのです。結果的に、日本語の使い方にも丁寧さが増し、子どもに説明するときの語彙や表現の幅も広がったように思います。
まとめると
親子で「日本語と英語の違い」を学ぶメリットは、
-
語学力の基礎が育つ
-
「なんで?」と考える習慣がつく
-
多様な考え方を受け入れる力が育つ
-
親子で学びの楽しさを共有できる
という4つです。どれも机の上の勉強だけでは得にくいもので、生活の中で自然に身につくのが魅力です。
まとめ|日本語と英語の違いを楽しく学ぼう
日本語と英語の違いは、音や語順だけでなく、その国の文化や価値観までも映し出しています。子どもにとっては「不思議」で「楽しい」発見の連続です。家庭では、身近な例や歌、絵本を通して自然に伝える工夫をすると、学びがぐっと身近になります。ぜひお子さんと一緒に、「日本語と英語のちがい探し」を遊びながら楽しんでみてください。


