「七夕って、どうして願いごとを書くの?」
ある日、娘にそう聞かれて、私は言葉につまってしまいました。毎年なんとなく短冊を飾っていたけど、そういえばちゃんと由来を説明したことがなかったかも…。
この記事では、七夕の由来や短冊に願いごとを書く意味を、子どもと一緒に学べる形でご紹介します。願いを書く楽しさだけでなく、その背景にあるお話や思いを知ることで、七夕がもっと特別な日になりますよ。
わが家の“七夕エピソード”|はじまりは素朴な質問から

子どもに聞かれた「なんで願いを書くの?」
「ねえママ、どうして七夕の日にお願いするの?」
ある日の夕食後、娘がそうぽつりと聞いてきました。
保育園で七夕の制作をしたらしく、家に持ち帰った小さな短冊には、まだひらがなで書くのもおぼつかない「おおきくなったら うたのせんせいになりたい」との文字が。
私は笑顔で「すてきな願いごとだね」と返しつつ、娘の問いかけにドキッとしました。
毎年、笹に短冊を吊るしたり、そうめんを食べたりして「七夕っぽいこと」をしてきたけれど、そういえば「なんで願い事するの?」なんて、ちゃんと話したことがなかったなと。
私自身も「織姫と彦星が年に一度会えるから…」くらいしか分かっていないことに気づき、なんだか恥ずかしい気持ちにすらなりました。
一緒に調べてみることに
「ママもちゃんとは知らないから、一緒に調べてみようか」
そう提案すると、娘は目を輝かせて「うん!」と即答。
翌日、図書館に行って七夕の絵本や民話の本を借りてきたり、一緒にスマホで「七夕 由来 子ども向け」などで調べたりしてみることにしました。
絵本には、優しい色合いのイラストで描かれた織姫と彦星の物語があり、娘は静かに聞き入っていました。
ネットで調べてわかったことを娘に話すと、「へぇ〜!」と何度も感心した表情を見せてくれて、いつもより親子の会話も弾みます。
こういう「知らなかったことを一緒に知る時間」って、知識だけじゃなく、子どもの心に小さな種をまく時間なんだなと感じました。
七夕の由来ってなに?|織姫と彦星の伝説
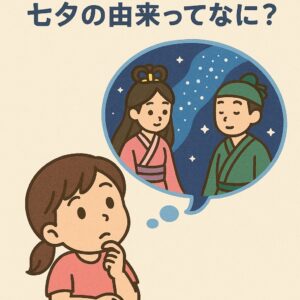
もともとは中国の伝説だった
私たちの知っている七夕の物語、実は中国の伝説「乞巧奠(きこうでん)」がルーツだそうです。
これは、織物が得意な「織女(しょくじょ)」と、牛の世話をする「牽牛(けんぎゅう)」という若者の話に由来しています。
日本には奈良時代にこの風習が伝わり、宮中での年中行事として定着していきました。やがて庶民の間にも広がり、現在の「七夕まつり」の形になったといわれています。
「日本だけの行事じゃなかったんだね」と娘がつぶやいたのが印象的でした。
“自分が知っていること”が、実は外国から来ていたものだと知るだけでも、子どもの視野って少し広がるんですよね。
働き者だった2人に起きた“ある出来事”
織姫と彦星は、天の川を挟んで住む、空の国の住人。
織姫は天帝の娘で、毎日毎日、美しい布を織る仕事をしていました。彦星は働き者の牛飼い。ふたりとも、仕事に一生懸命な若者でした。
そんなふたりが出会い、結婚することを天帝も認めます。
でも、結婚後は…なんとふたりとも仕事そっちのけで、毎日いっしょに遊んでばかりになってしまったのです。
その様子を見た天帝は怒り、「ちゃんと働くまでは会っちゃダメ!」と、2人を天の川の両岸に引き離してしまいます。
でも、娘を想う父としての心もあったのか、「年に一度だけ、7月7日だけは会ってもいいよ」と条件をつけたのです。
この話をすると、娘はじっと考え込んだあと、
「なんかちょっとかわいそうだけど、うれしい日だね」
と、ぽつり。
大人から見ると「ちゃんと働かないとね」って思うけど、子どもは純粋に「会えるってすてきだね」って感じるんですよね。その素直さが、なんだか胸に響きました。
どうして“願いごと”をするの?|短冊にこめた想い
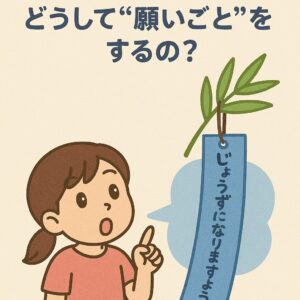
もともとは“手習い”の上達祈願だった
「どうして短冊にお願いを書くの?」という素朴な疑問。
その答えを調べてみると、なんと江戸時代の“手習い文化”にたどり着きました。
当時の七夕は、織姫が“機織りの名手”だったことにちなんで、「自分の手仕事が上達しますように」という願いを込める日だったそうです。
特に女の子は、「字が上手になりますように」「裁縫がうまくなりますように」と、努力によって叶えたい願いを書くことが多かったとか。
「今の“将来なりたいもの”とは、ちょっとちがう願い方だったんだね」と話すと、娘も「むかしの人はがんばる願いが多かったんだね」と不思議そうな顔。
さらに調べると、短冊の色にはそれぞれ意味がありました。
-
青(緑):人間力・成長
-
赤:感謝・父母への思い
-
黄:人との信頼・人間関係
-
白:義務・決まりを守る心
-
黒(紫):学問・修行
「じゃあ、字がうまくなりたいなら、紫?」
「お友だちいっぱいできるようにって願うなら、黄色かな〜」
と、短冊の色選びすらちょっとした会話のタネになります。
今は“なんでも願っていい”時代
現代の七夕では、願いごとにルールなんてありません。
「健康でいられますように」「家族が仲良く過ごせますように」から、「ケーキを毎日食べたい」や「鬼ごっこで負けませんように」まで、本当に自由。
わが家でも、娘が書いた短冊には、「うたのせんせいになりたい」「あしたもえがおでいられますように」など、その時々の気持ちがあふれています。
息子(当時3歳)は、まだ字が書けないけど「アイスたべたい」と言うので、代わりに私が書いてあげました。
本人は満足げにその短冊を笹につけて、「これ、かみさまにとどくかな?」と真剣な顔。
こういう時間って、大人が横から「そんな願いじゃだめよ」なんて言うべきじゃないなと、つくづく思います。
むしろ、「いまのこの子が何を大切にしてるか」が見える、大事なヒント。
だから私は、願いごとそのものより、その奥にある“子どもの世界”を大切にしたいと思うようになりました。
わが家流・七夕の楽しみ方|飾りつけから会話のタネまで
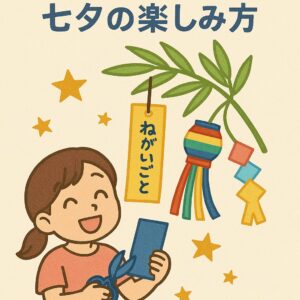
折り紙と100均アイテムで手作り短冊
「七夕だからって、特別なことはしなくていいんじゃない?」
そう思っていた私が、今では毎年ちょっと気合を入れて準備するようになったのが、手作りの短冊と飾りつけです。
用意するのは、100円ショップで買える以下のアイテム。
-
カラーペーパー(五色)
-
麻ひもやタコ糸
-
洗濯ばさみ(ピンチ)やマスキングテープ
-
小さな折り紙や星型シール
「今日は短冊デーね!」と決めた日に、みんなでリビングに集まって、わいわい言いながら願いごとを書きます。
「去年も“プリンセスになりたい”って書いてたよね」
「パパの“腰が痛くなりませんように”って、渋いよね」
なんて、ちょっとしたツッコミや笑いが生まれるのも、七夕ならではの風景です。
リビングの壁に貼った麻ひもに、短冊をピンチで挟んで吊るせば、即席の“願いコーナー”の完成。
夜になると、少しだけ照明を落として、飾った短冊を家族で眺めるのが恒例になりました。
七夕ごはんも“特別感”で
もうひとつ、七夕の楽しみといえば「七夕ごはん」。
とはいえ、豪華なごちそうではありません。“星”をテーマにしたちょっとした工夫が大事。
たとえば、
-
そうめんに星形に抜いたにんじんやオクラをトッピング
-
星型ゼリーやフルーツを盛ったデザートプレート
-
星型のおにぎりを作ってお弁当風にする日も
娘は「星のにんじんだー!」とテンションアップ。
夫も「なんかこれだけで気分が七夕になるなぁ」と笑顔に。
夕食後には「今日はどんなお願いをしたの?」なんて話をするのも、家族の会話が広がる時間です。
親として感じた“願う”ことの大切さ

願いごとって、心を見つめる時間かもしれない
「こうなりたい」「こうなってほしい」——
そんな想いを、たった数行の短冊に書き込む時間。
それは、大人にとっても子どもにとっても、自分の気持ちや未来を見つめる、静かな時間なのかもしれません。
実際、娘に「何をお願いしたい?」と聞いたとき、
「うーん……まだわかんない」としばらく考え込んでいたのが印象的でした。
最終的に書いたのは「うたのせんせいになりたい」だったけど、そこに至るまでの“迷う時間”が、すでに心の成長につながっている気がしたんです。
願いごとって、必ずしもすぐに決められるものじゃない。
「なにを大切にしたいのか」「どんな未来がいいのか」
そんなことを考えるきっかけになるからこそ、短冊ってすごく価値ある存在なんだなと感じました。
私自身、子どものころは「お金持ちになりたい」とか「マンガ家になりたい」なんて書いていたけれど、大人になってから「家族が健康でありますように」と願うようになったように、願いごとは“そのときの自分”が表れる鏡なんですよね。
だからこそ、子どもが何を書くかを見守るのは、単なる行事参加じゃなく、親子の心を見つめ合う機会なんだと思います。
子どもの願いに、親ができること
「うちの子、こんな夢を持ってたんだ」
短冊を見て、そう思ったことが何度もあります。
普段は照れて言わないような夢や、テレビで見たものから憧れた仕事、時にはちょっと笑っちゃうような“子どもらしい願い”まで――。
そのひとつひとつに、その子なりの想いがあるんですよね。
そんなとき、親としてついやってしまいがちなのが、「そんなのムリだよ」とか「もっと現実的なことにしなさい」といった“大人目線のフィルター”で願いを見てしまうこと。
でも、それは子どもの心に“否定”として残ってしまうかもしれない。
だからこそ私は、「いいね」「応援してるよ」と、まずは受け止める姿勢を大切にしたいと思うようになりました。
「どうしてそれを願ったの?」と聞くことで、子どもが話してくれる背景には、
「お友だちがピアノの先生になりたいって言ってたの」
「テレビで見た宇宙がかっこよかったの」
そんな小さな“きっかけ”があることも多いです。
それを聞けるだけでも、親としてはうれしいし、「この子の今を知れたな」と感じる時間になります。
応援すること、信じて見守ること、そして共感すること。
それが、願いごとのそばにいる親にできる一番の“魔法”なのかもしれません。
まとめ|願う気持ちを、親子で大切にしよう
七夕は、ただの“飾りつけイベント”ではありません。
それは、親子がそれぞれの心と未来に向き合う、大切な年中行事です。
「願いごとを書く」——そのシンプルな行動の中には、
子どもの想いや夢、そして親の気づきや愛情がたくさん詰まっています。
その背景にある“由来”や“意味”を少し知るだけで、短冊を吊るす時間はぐっと深く、あたたかいものに変わります。
子どもの願いに、意味を求めすぎず、正しさを求めすぎず、
ただそっと寄り添って、「あなたの願い、ちゃんと届くといいね」と伝えてあげる。
そんな時間が、きっと親子の絆を育ててくれるはずです。
今年の七夕、あなたもお子さんと一緒に、願いごとの意味を話しながら、心の中に小さな希望の種をまいてみませんか?


